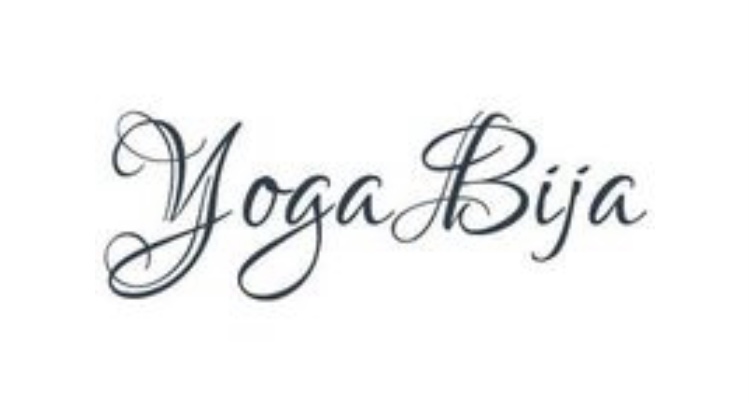プラーナーヤーマに欠かせない【クンバカ】①〜二つの意味
ここ最近、プラーナーヤーマについて何回か書いていますが、改めて【プラーナーヤーマ】とは?
⚫️プラーナーヤーマとは、プラーナ(気・エネルギー)という言葉とアーヤーマ(停止、延ばす、広げる)という言葉からなっています。
⚫️文字通り、呼吸を通して体内にプラーナを取り入れ、それを身体中にみなぎらせることです。
⚫️古代のヨーギーは、深くて静かにコントロールされた呼吸は、単に心を落ち着かせ身体をリラックスさせてくれるだけではなく、身心をエネルギーでいっぱいにしてくれることを、体験を通して知りました。
⚫️さらに詳細に観察していった結果、身体の中をプラーナが流れる道があることを知り、それをナーディーと呼びました。なかでも、身心に影響を与える重要なナーディーが三本あることを知りました。イダー、ピンガラー、スシュムナーの三本です。
⚫️三本の中でもスシュムナーに、プラーナを自由に流すことが重要であることを悟りました。そのためには、呼吸を止め、身体に入ったプラーナを外に出て行かない方法を作りました。それがクンバカやバンダです。
以上、一言ではなかなか伝えきれないものです。
呼吸法と言われることが多いけれども、もっと奥が深いです。
『ヨーガ・スートラ』とプラーナーヤーマ
まずは、『ヨーガ・スートラ』とは?
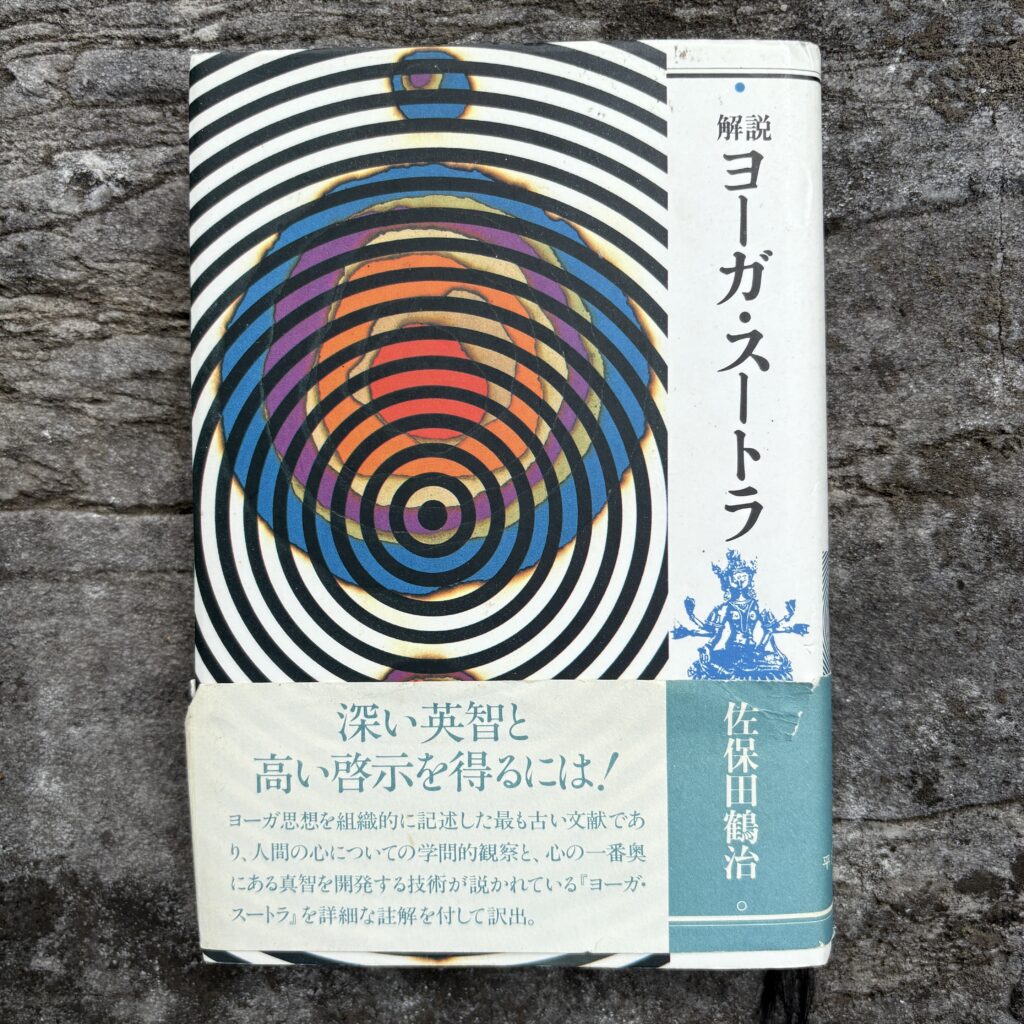
⚪︎成立年代
『ヨーガ・スートラ』自体が、一時期にひとりの作者によって、短期間の間に書かれたわけではありませんので、正確な成立年代を特定することはできません。学者や研究者の間にも様々な意見があるようです。
ところで、『ヨーガ・ スートラ』の成立にあたっては、仏教哲学の影響を大変受けています。一方的に受けているというよりも相互に影響しあっています。それは、教典の中に仏教語がいくつか見られることで容易に推測されます。
『ヨーガ・スートラ』の理論的な面は、サーンキヤ哲学が基本ではありますが、仏教哲学の影響を受けていることも知っておかなくてはなりません。 そのおかげとでもいいましょうか、成立年代のはっきりしている仏教経典群や『ヨーガ・スートラ』の注釈書などの比較研究により、おおよその成立年代は知ることができます。
スートラは全体で4つの章から成り立っていますが、そのうち第1章から第3章までが450年以降に、第4章がやや遅れて550年以降に成立し、遅くとも6世紀までには現在の『ヨーガ・スートラ』が成立したことが知られています。
⚪︎著者・編纂者
インドではその作品がどれだけ古来からの伝統を持っているかが問題にされる事はあっても、誰が書いたかと言う作者の名前はあまり重要視されないと言われています。これは『ヨーガ・スートラ』にも言えることです。よくパタンジャリの『ヨーガ・スートラ』と呼ばれますが、決してパタンジャリという人物がこの教典の全編を表したわけではありません。しかしパタンジャリの『ヨーガ・スートラ』と言うぐらいですから、何らかの関わりを持っていた事は確かなようです。
パタンジャリという名前は、一般にはサンスクリット語文法の注釈書『マハー・パーシャ』を著した紀元前、2世紀頃の大文法家の名前として知られています。ただ、『ヨーガ・スートラ』と、紀元前2世紀ごろに活躍したパタンジャリでは、600年以上もの時代のずれと言う決定的な矛盾が出てきてしまいます。
①パタンジャリ編纂説
それまでのヨーガや実習に関する諸々の説に、文法家でパタンジャリがヨーガに関する自らの意見や体験をまとめて 編纂したという考えです。つまり、パタンジャリは編纂者であるという説です。
②一部を書いた説
『ヨーガ・スートラ』の中では、第2章28節から第3章55節までが最も古い部分と言われていますが、この部分こそ、紀元前の大文法家パタンジャリの作であると主張するハウエルという学者の意見もあります。そして、この部分を書いた大文法家パタンジャリの名前にちなんでパタンジャリの『ヨーガ・スートラ』と呼ばれていると言うのです。これならば、前のような時代の問題は解決できます。
③別人パタンジャリ説
文法家パタンジャリとは同性別人で、たまたま『ヨーガ・スートラ』を編纂したのは、パタンジャリと言う人物だったと言う説です。
⚪︎『ヨーガ・スートラ』の構成
第1章
ヨーガの定義/心の働きと分析/修習と離欲/三昧の定義/自在神/心の静澄/定の定義
第2章
行事ヨーガ/修行の障害になる五つの煩悩/除去すべき苦/三昧に達する為のヨーガ修行法/八つの修行
第3章
八つの修行の続き/綜制により得られる超自然力
第4章
転生とプルシャの独存について
⚪︎『ヨーガ・スートラ』のプラーナーヤーマ概略
プラーナーヤーマ ( 気、調息)
アシュターンガ・ヨーガでは、アーサナの次にプラーナーヤーマがきます。
『ヨーガ・スートラ』には第2章49節から53節で説明されています。
プラーナは生命を維持していくための根源的なエネルギーのようなものです。『チャーンドーギヤ・ウパニシャッド」(紀元前800年頃)などの古いウパニシャッドにもプラーナの重要性が説かれていますので、その当時すでにプラーナがよく知られていたことが分かります。
プラーナと心の関係も洞察力の深い人たちによって経験的に知られていました。わたくしたちの日常の生活においても、これは少し観察すれば分かることですが、呼吸が荒く乱れているときは心も平静さを失っている場合が多く、反対に心が落ち着いているとき、リラックスしているとき、何かに集中しているときなどは、呼吸も停止しているかのように静かです。
このように呼吸の流れと心の状態とには深い関係があり、瞑想によって心統一するヨーガ行者にとって、呼吸をどのように扱うかはたいへん重要な要素のひとつでした。ですからアシュターンガ・ヨーガにおいても、身体の準備ができていよいよ心統一する前の段階として、身体と心の架け橋としてのプラーナーヤーマは重要な意味を持ちました。おもしろいことに、西洋の修行法にはこの呼吸を利用する方法がほとんどないといわれています。プラーナーヤーマは東洋の叡智と呼ぶべきものかもしれません。
『ヨーガ・スートラ』におけるプラーナーヤーマは、ハタ・ヨーガのように身心を活性化させるという目的ではなく、むしろ身心を沈静化させるためのプラーナのコントロールと受け取ることができます。またその意味から、プラーナーヤーマは「調気」と訳されることもあります。
『解説 ヨーガ・スートラ』(佐保田鶴治:著)に書かれているプラーナーヤーマについて
○『解説 ヨーガ・スートラ』という本について
出版元の平河出版社のホームページから
深い英智と高い啓示を得るには! ヨーガ思想を組織的に記述した最も古い文献であり、人間の心についての学問的観察と、心の一番奥にある真智を開発るす技術が説かれている『ヨーガ・スートラ』の全体を詳細な註解を加えて訳出する。
○佐保田鶴治博士について
成瀬貴良先生からよくお話しを聞いていました。
日本ヨーガ禅道友会のホームページを見てみると、最初の『解説 ヨーガ・スートラ』は恒文社から出版されていて、なんと私の生まれた年と同じでした。
その後、1980年に改訂版として平河出版社から出版されたようです。
日本ヨーガ禅道友会のホームページから、佐保田鶴治博士について。
佐保田鶴治氏はインド哲学の学者です。
京都帝国大学文学部を卒業後、立命館大学、大阪大学で30数年間教授生活を送りましたが、若いころから虚弱体質で、60歳を越えるまで、満足な健康感を味わったことがなかったと言います。そこで大学を退官してから、あるインド人にヨーガの手ほどきを受け、自らも研究し、日々ヨーガ実践の生活に入ったところ、今までの自分が信じられないほどの健康感を獲得することができたと言います。以来、請われるままに人々にもヨーガを教える身となりましたが、20数年間に及ぶヨーガ普及の功績は、亡くなってから38年を経た現在でも多くの教え子達の手によって受け継がれています。(『ヨーガ入門』より)
数多くのヨーガ関連の本を書かれ、そして実践もされた大先輩です。
60歳を過ぎてからというところも魅力を感じます。
いくつになってもヨーガはできることを実践されました。
○内容
調気法
2-49
さて、坐りがととのったところで、調気を行ずる。
調気とはあらい呼吸の流れを絶ちきってしまうことである。
調気法(pranayama)を定義して、あらい呼吸の流れを絶ちきることであるというのである。あらい呼吸は前に(1-31)手足のふるえなどと並べて、心の散動状態の随伴現象として挙げられている。調気を定義するのに、われわれの通例の呼吸の仕方をやめてしまうという面をとりあげたのは面白い。われわれの日常の呼吸は、短かくて、不ぞろいである。ある人の書いたものによると、ヨーロッパ人は通常、1分間に30回の呼吸をなし、かつ長短まことに不均等であるという。この短かくて、不そろいな呼吸をゆるやかでリズミカルなものにすることが、調気の外部的な特長である。元来プラーナというのは、息のことではなくて、身体の中や大気中にある生命の素である。宇宙的生命エネルギーと解してもよい。呼吸の息がプラーナではなくて呼吸させるものがプラーナなのである。このプラーナは、もとは吸う息の中に含まれて身体の中へ入ってきたものである。
2-50
調気は出息と入息と保息とからなり、空間と時間と数とによって測定され、そして長くかつ細い。
出息、入息、保息という訳語は実は便宜的なものである。原文では、外部へ向かうはたらきと、内部へ向かうはたらきと、停頓するはたらきを有する、となっている。この三つのはたらきを、ただちに出息(レーチャカ)、入息(プーラカ)、保息(クンバカ)に当てることが妥当であるかどうかは問題である。作者は気息のことをいっているのではなくて、生気のことを言っているのではないかと思われる。
空間によって測定するというのは、例えば出息の時には、鼻のさきに下げた軽い葉片または綿毛がどれだけの距離で動くかを調べるとか、入息の時には、かかとから頭頂に至る間のどこかで、蟻の違うようなむずがゆさが起こることによって測定するとかすることである。時間によって測定するというのは、クシャナやマートラーなどの時間単位を以て気息の長さを測定して、標準の長さにそろえること。クシャナ(刹那)は瞬きするのに要する時間の四分の一の長さの時間(3-52参照)、マートラーは、まず手のひらで膝小僧を三度さすった後で、親指と人さし指とでパチッと音を立てるのに要する時間の長さである。数を以て測定するというのは、呼吸の回数を以て気息の上昇を測定することをいう。例えば、初級の気息の上昇には、36呼吸を以てするというようにである。気息の上昇というのは、気(ヴァーユ)が鼻のつけ根の処から押し上げられて、頭に突きあたることをいう。ある註釈家は、マートラーを以て測定するというのは、数を以て測定するというのと同じであるという。そのわけは、健康人の一呼吸の時間は1マートラーの長さであるからである。この原文はどうも充分に理解しつくされているとは思えない。註釈家の見解は後世のものであるし、その見解の間に不一致な点がある。調気の法は今日同様、直伝による点が多かったのであろう。調気法は、その後益々発達して、ハタ・ヨーガの中心的な行法となる。
ここで保息(クンバカ)が出てきますが、佐保田先生は「妥当であるかどうかは問題である」と書かれていて「正気のことではないか?」という結論で終わっています。
また正気についてここでは言及されていませんがプラーナのことだと推察します。
さらにチダーナンダジーの『幸福への道』(スワミ・チダーナンダ:著/増田喜代美:訳/自費出版)から、
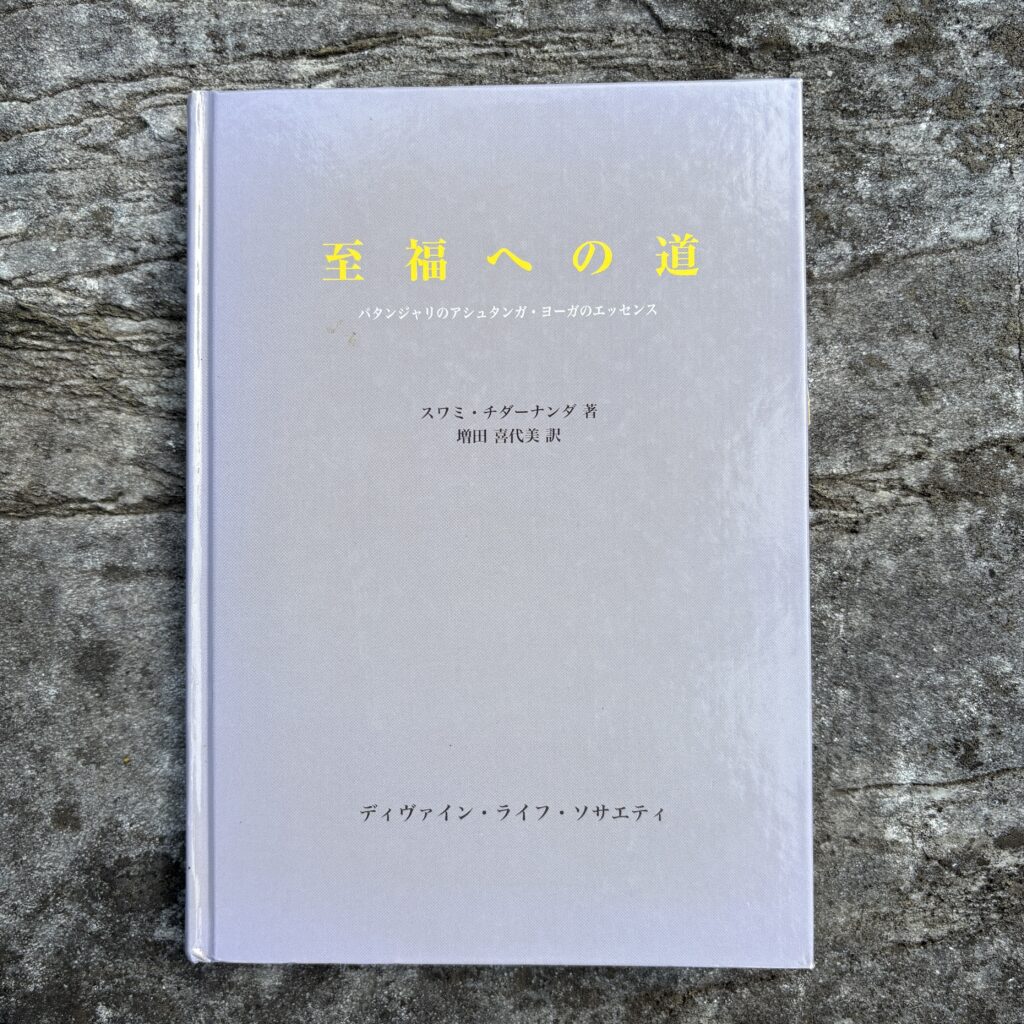
その後、東方出版からタイトルと装丁が変わり『八段階のヨーガ』が出版されているので、今ではAmazonでも購入可能です。
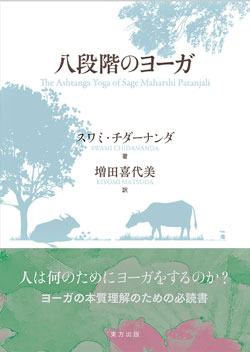
*写真は東方出版からお借りしました。
『幸福への道』は
紀元前のインドの賢者・パタンジャリの『ヨーガ・スートラ』の一部を解説したもので、特に「八段階のヨーガ」(アシュターンガ・ヨーガ)について
詳細に解説している。
(*こちらもAmazonから引用しています。)
その中でプラーナーヤーマの解説を見てみると
プラーナーヤーマ(調気)は、ラージャ・ヨーガの第四段階です。パタンジャリは、最も科学的な方法によって、人間の一番外側の鞘からスタートし、ゆっくりとより精妙な鞘へと進んでいきます。呼吸と心は、密接に相互依存・相互浸透し合っています。呼吸のコントロールとは、吐く息と吸う息の流れを止めることを意味します。呼吸は、身体の中にある精妙な生命エネルギーの粗雑な表れなのです。例えば時計のねじのつまみをつかんで、それを作動できなくさせてしまうと、より精妙な歯車が、そしてついには最も精妙なひげぜんまいが停止してしまうのです。同様に、心を作動させるエネルギーをコントロールすることによって、心はその動きを停止するのです。この、心を動かしているものがプラーナ(気)なのです。もしプラーナ(気)が停止させられれば、心は動くことができず、心の静止状態がやってくるのです。
次の節も先ずは佐保田先生の解説から。
2-51
第四の調気は、外部及び内部の測定対象を充分に見きわめた後になされる止息である。
第四というのは、出息、入息、保息に次ぐ調気であることを示す。外部の測定対象とは、出息の際に鼻頭からどれだけの距離にある軽いものが動くか、また入息の際に心臓から臍に至る間のどこに気の動く感じがあるかなどという測定をいう。こういう測定を一切捨て去って、出入の息が止まることをいう。これは第三の保息に似ているが、違うところは、保息の場合にはやはりいろいろな測定基準があるし、また呼吸についての充分な観察の後になされたものでないが、この第四の調気の場合は、それ以前に充分に内外の対象を見きわめた後に息をとめるのである。このように註釈家は説明しているが、果たして原経文の真意を掴んでいるかどうかは疑問である。原文をすなおに読めば、「内外の対象をことごとく捨て去ったのが第四の調気である」ということになる。ハウエル氏は、第四の調気を、深い禅定のうちに自然に行なわれる深くて微細、息が絶えているかのように見える呼吸のことと解している。ヴィヴェーカーナンダの如きも本経文を理解し得なかったと見えて、全く見当外れな訳をつけている。あるインドのヨーギーによると、調気法を行じていると、いつの間にか呼吸が止まっているという。
チダーナンダジー:
故に、プラーナ(気)の流れを止めることをプラーナーヤーマ(調気)といいます。しかし、それはハタ・ヨーガの本に載っている9、10種類のプラーナーヤーマのことではありません。ここでいうプラーナーヤーマは、ハタ・ヨーガのプラーナーヤーマをさしてるのではなく、“クンバカ(止息)”に関することだけに言及しているのです。息を吸ってから止めることを“内的クンバガ”といいます。また、息を吐いてから止めることを“外的クンバカ”といいます。内的にせよ外的にせよ、時々自然に息が止まることがあります。これを“ケーヴァラ・クンバガ”といいます。
佐保田先生:
2-52
調気を行ずることによって、心のかがやきを覆いかくしていた煩悩が消え去る。
心のかがやきというのは心を構成する三徳の中のサットヴァ・グナの性格をさしている。このサットヴァ性においてすぐれている覚は通例無明等の煩悩によって覆いかくされているから、その固有の照明性を発揮することができない。調気の修行を励行することによって、このしきり(へだて)が消えるから、心のかがやきがあらわになって、解脱へみちびく弁別智(真実の自己とエゴを識別する力)が生ずるのである。
チダーナンダジー:
プラーナーヤーマ(調気)によって、人間のすべての内的器官は浄化されるのです。私たちは、人の中には、サットワ・グナ(純質)とラジャス・グナ(動質)とタマス・グナ(暗質)があることを知っています。我々の目的は、サットワ・グナを最大限に発現させることなのです。しかし、サットワ・グナを覆い隠してしまっている汚れや曇りのヴェールがあるのです。プラーナーヤーマ(調気)はこのヴェールを取り除いてくれ、サットワ・グナを完全に発現させてくれるのです。これがプラーナーヤーマ(調気)の主な目的なのです。
佐保田先生:
2-53
その外、意(マナス)がいろいろな凝念に堪えられるようになる。
講気の第二の結果を述べている。この経文の内容は1-34に説くところと、主旨において一致する。意(マナス)はインド心理学で根(インドリア)(心理器官)の一つに数えられている。というのは、意は他の10の感覚、運動の器官と結んではたらく場合が多いからである。意の機能は思惟(サンカルパ)であるといわれる。ここで思惟というのは、思考作用と意志作用とを兼ねた心理作用である。注意の作用もまた意に属している。だから凝念(ダーラナー)をはじめとする心理操作はすべて意のはたらきによってなされている。意と凝念との関係は古くはカタ・ウパニシャッドの中にも出ている。凝念については3-1で説明される。
チダーナンダジー:
人はゆっくりと心の動きを止めていかなければなりません。
心とプラーナ(気)は密接に関連しあっているので、プラーナ(気)を調整することによって心を調整するのです。
その結果、心は浄化され、それによってサットワの完全な発現を邪魔していたヴェールが取り除かれるのです。
サットワの輝きが現れ出たとき、あらゆる善なる想念がやって来て、人はヤマ・ニヤマの上に確立するのです。
すべては申し分ないものとなっていきます。
心はゆるぎなく安定し、次の段階である“ダーラナー(集中)”の実践への適性を獲得するのです。
このように、プラーナーヤーマ(調気)の目的は、修行者を“集中”の実践に適するように準備させることなのです。
このように、お二人とも同じような解説です。
スートラのような教典は、本文は簡潔にしか書かれていないので、解説が大切だとよく言いますが、読み比べてみることでその意味が本当によくわかります。
ハタ・ヨーガのプラーナーヤーマ
○ハタ・ヨーガとは?
これも何回もご紹介しているかもしれないので、わかっている方は先に進んでくださいね。
ヨーガの流派としては比較的新しいもので、10世紀以降に体系化されました。
しかし、『マイトラーヤナ・ウパニシャッド』(紀元前200年頃)の中にはすでに、ハタ・ヨーガでは重要な意味を持つスシュムナーや、重要なテクニークのひとつであるケーチャリー・ムドラーと思われるものがあり、一概に新しく成立したヨーガとは言いきれません。体系づけられたのは他のヨーガと比べると新しいかもしれませんが、その起源は相当古いものと思われます。
ハタ・ヨーガのハタとは「力」「努力」「暴力」という意味で、ハタ・ヨーガを直訳すれば「力のヨーガ」という意味になります。また、教義的な解釈としては、ハ(ha)を太陽あるいは陽エネルギー、タ(tha)を月あるいは陰エネルギーと解することもあり、この二つのエネルギーのバランスをうまくとることをハタ・ヨーガの目的とするという考え方もあります(ハを「月」、タを「太陽」とすることもある)。
古典的なラージャ・ヨーガが瞑想を中心とした心理的な操作を主体とするヨーガであるのに対して、ハタ・ヨーガは、心や精神だけではなく、それをも含んだ身体全体を通して解脱に至ることを説いているという特徴があります。ラージャ・ヨーガでは重視されていなかった身体というものを、ハタ・ヨーガでは、人間の個体を大字宙に対する小宇宙として、重要で聖なるものとして扱います。ですからハタ・ヨーガでは、必然的に身体に関するテクニックがたくさん開発されました。
佐保田鶴治博士は、さまざまなヨーガの流派の中で、このハタ・ヨーガこそがヨーガとしての特徴をもっていると主張されています。なぜならば、バクティ・ヨーガやラージャ・ヨーガは、それぞれキリスト教や禅の中にもその形をみることができるからです。
○ハタ・ヨーガのプラーナーヤーマ
プラーナーヤーマは「プラーナ」(息、呼吸、生気、生命力)と「アーヤーマ」(延ばす、広げる、止める)という二つの言葉からできています。ですから、プラーナーヤーマとは、生命エネルギーとしてのプラーナを体内に蓄え、身体の隅々に拡散させる方法ということになります。また、プラーナを体内に止めるという意味から「クンバカ」(止める)とも呼ばれます。クンバカとは「壺」や「かめ」のことですが、それは、呼吸を通じて体内に取り入れたプラーナを、壺やかめに水を満たすように蓄えることを意味しています。このように、プラーナーヤーマの特徴はその名前のとおり、呼吸を止めること、つまり「止息」「保息」にあります。一般に呼吸は「レーチャカ」( 吐息)「プーラカ」( 吸息)からなっていますが、プラーナーヤーマではそれに「クンバカ」(止息)を入れるのです。
これらはゆっくりと慎重に進めていかなくてはなりません。また、レーチャカとクンバカとプーラカとの比率は一概にはいえませんが、それぞれ2:4:1が理想的であるといわれています。
プラーナーヤーマは「呼吸法」とも訳されますが、単に呼吸の仕方であったり、酸素を有効に取り入れるだけの方法として扱っているわけではありません。前述したように、それは呼吸を通して体内に新鮮な生命力であるプラーナを取り入れ、身心を活性化する重要なテクニックです。
プラーナーヤーマは肉体と心とをつなぐもので、呼吸器官という意識的に操れる器官を通して心や精神を抑制できるところから、瞑想の初歩的な段階にも用いられます。これがラージャ・ヨーガでのプラーナーヤーマの大きな役割です。それに対してハタ・ヨーガでのプラーナーヤーマは、瞑想のための身心の沈静化を目指すよりも、むしろプラーナの活性化にあります。
ここでやっと【クンバカ】に辿り着けました。
次回はさらに深掘りしていきたいと思います。
プラーナーヤーマが学べるクラス開催中
毎週木曜日、不定期土曜日開催!
次回は
第3回 『ハタ・ヨーガ・プラディーピカー』第2章/ バンダ
【清水町】9/18【オンライン】10/4

【オンライン】10/4

第4回 『ハタ・ヨーガ・プラディーピカー』第2章/ プラーナーヤーマ
【清水町】9/25【オンライン】10/11

【オンライン】10/11

ご予約・お問い合わせなど
●LINE
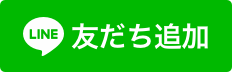

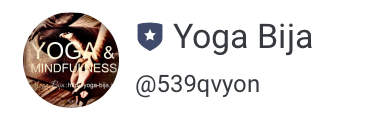
●問合せ:090-7912-2282 / ylsbija@gmail.com
最後に
長文になりましたが、最後までお読みいただいてありがとうございます。
提示していない引用元は『いまに生きる インドの叡智』(成瀬貴良:著/善本社)からになります。
この本はヨーガが生まれたインドを背景に歴史と共にヨーガを学べるテキストです。
なので、ひとりで読むのは難しいかもしれません。
ご興味のある方がいらっしゃればいつでも学習会をスタートできます。
お気軽にお問い合わせくださいね。
Yoga Bija
加藤